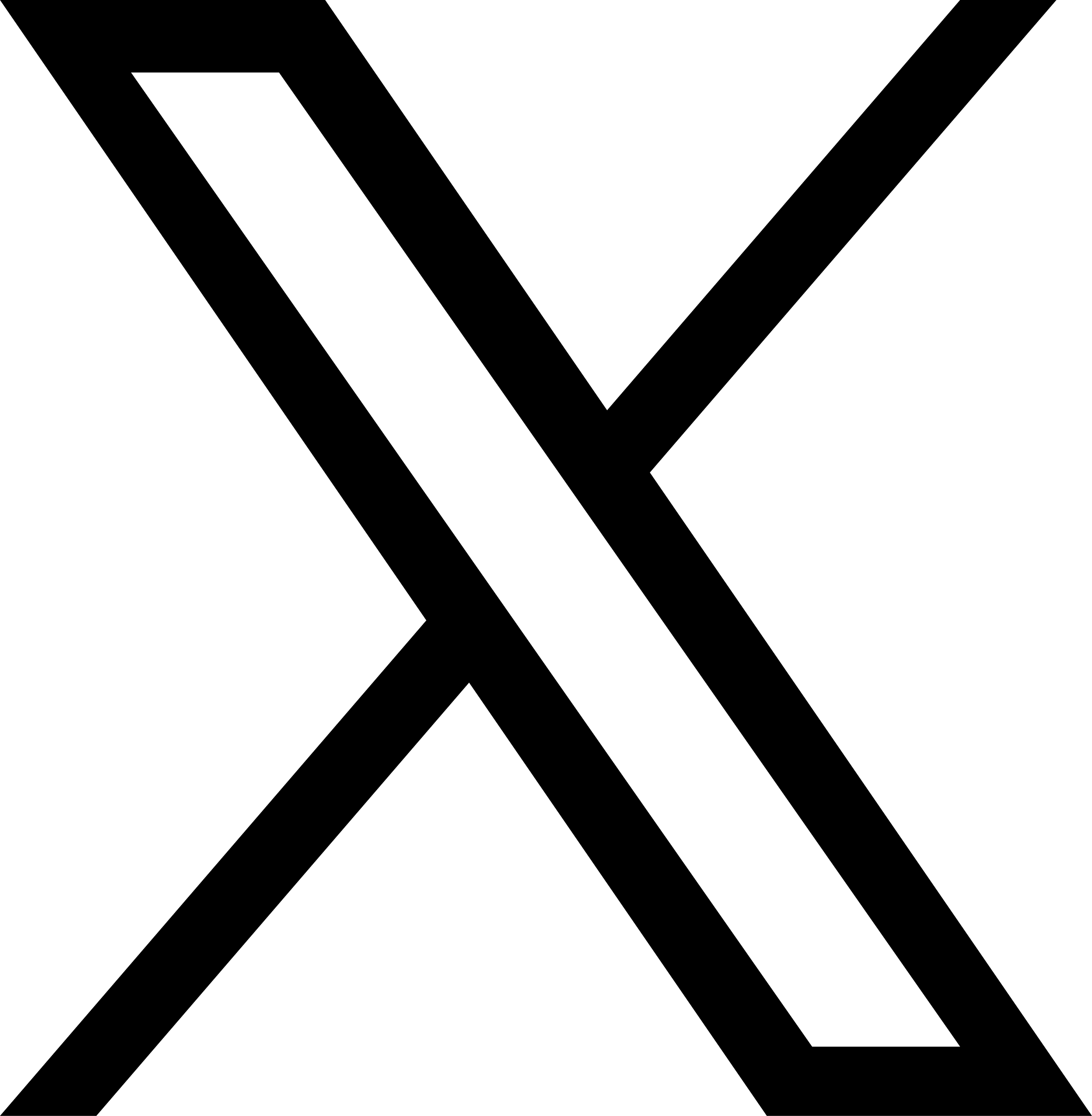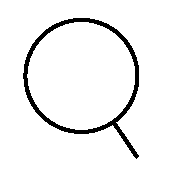デ・キリコ“幻想的な静謐さ”を湛えた形而上絵画など、代表作が一堂に -「デ・キリコ展」東京都美術館で

カステッロ・ディ・リヴォリ現代美術館(フランチェスコ・フェデリコ・チェッルーティ美術財団より長期貸与)
© Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Rivoli-Turin, long-term loan from Fondazione Cerruti © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024
同時にマヌカンは、その謎を帯びた様相でもって、存在の意味を探究する人間の神秘的な側面を表すものでもあった。それが、ミューズや予言者だ。たとえば、マヌカンを描いた最初期の傑作とされる《予言者》では、イーゼルの前で熟考する画家の姿として、腕のないマヌカンが描かれている。その後、デ・キリコは、《形而上的なミューズたち》や《不安を与えるミューズたち》など、マヌカンを題材に数々の代表作を生みだしている。
古典への回帰
第一次世界大戦後の西欧美術では、古典へと回帰する動きが広く見られた。つまり、前線・銃後ともに甚大な犠牲を強いたこの大戦を経験した人々は、秩序を重んじ、前衛表現よりも伝統に目を向るようになった。

© Giorgio de Chirico, by SIAE 2024
デ・キリコも例外ではない。1919年、ローマ・ボルゲーゼ美術館のティツィアーノの作品を目にしたデ・キリコは、「偉大な絵画とは何か」ということに目を開き、ルネサンス絵画の技法に目を向けてゆくことになる。古代彫刻が佇む岸壁を、入念な筆致で描いた《オルヴィエートの岸壁の形而上的記憶》などは、こうした流れのなかで手がけられた。
古典絵画研究の中断

© Giorgio de Chirico, by SIAE 2024
デ・キリコの古典への傾倒は、1930年代以降も続くもののの、パリに戻った20年代後半には、古典絵画研究が一時的に中断されている。当時、パリで興っていたシュルレアリスム運動に呼応して、形而上的な主題に改めて取り組むようになったのだ。

ナーマド・コレクション
© Nahmad collection © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024
しかしそこにも、古典の息遣いは感じられるのではなかろうか。《神秘的な考古学者たち(マヌカンあるいは昼と夜)》といったマヌカンを描いた作品では、過去の作品に比べてマヌカンはより人間的な姿をしている。また、《哲学者の頭部がある形而上的室内》においては、室内を題材としつつもモチーフは一新され、そこには古代彫刻や神殿を見てとることができる。
古典への関心の再燃

ウフィツィ美術館群ピッティ宮近代美術館
© Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024
こうした中断を挟みつつ、1930年代、デ・キリコの古典絵画への関心は再燃してゆくこととなった。その模範となったのが、印象派の代表的な画家でありながら、のちに古典主義へと回帰していったピエール=オーギュスト・ルノワールである。たとえば、マヌカンをモチーフとした《南の歌》は、かつての形而上絵画の均一な塗り方とは異なる、ルノワールのように繊細な筆致により、ボリューム感を引き出していることが見てとれる。

ローマ国立近現代美術館
© Giorgio de Chirico, by SIAE 2024
また、1932年の《横たわって水浴する女(アルクメネの休息)》は、ルノワール晩年の水浴画に基づくもの。その約10年後にデ・キリコは、同じ水浴の主題で《風景の中で水浴する女たちと赤い布》を描いているが、作風は大きく異なる。そこではむしろ、バロック絵画、ウジェーヌ・ドラクロワやギュスターヴ・クールベに着想を得て、濃密で艶やかな画面を作りだしている。

ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団
© Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024
このようにデ・キリコは、1920年代にはルネサンス、1940年代にはバロックと関心を移しながら、伝統絵画を消化していった。デ・キリコは古典に、いわば時間を超越する可能性を見てとっていた。これは、前衛芸術の「現代性=同時代性」とは対照的に、「無時間性」を志向するという意味で、時間が宙吊りにされたように静謐な形而上絵画と通底するものだといえるかもしれない。
晩年の「新形而上絵画」

ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団
© Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024
デ・キリコは晩年の1960年代、形而上絵画に改めて取り組んでいる。これらの作品は、「新形而上絵画」と呼ばれている。ここでデ・キリコは、自身がそれまでに描いてきたさまざまなモチーフを自在に組み合わせたり、変容したりすることで、新たな画面へと再構成していった。
ピックアップ


スケジュール



![fashionpress[ファッションプレス]](/img/common/logo_0119_1928.svg)